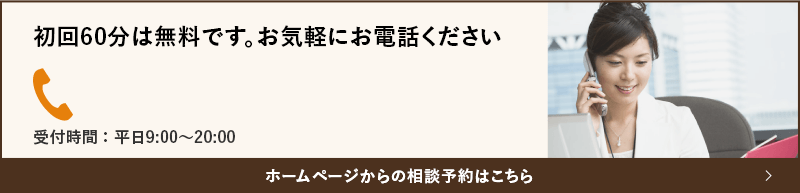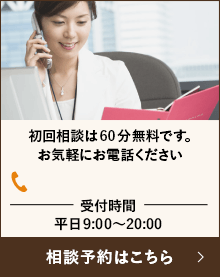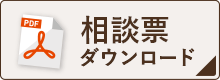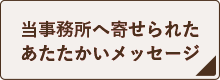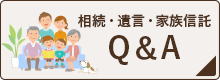不動産の遺産分割について、相続に詳しい弁護士が解説
不動産は、現金や預貯金のように物理的に分けるのが難しいことから、遺産の中に被相続人の自宅などの不動産があるケースでは、遺産分割トラブルが起こりやすい傾向にあります。
以下では、不動産を遺産分割する方法や、遺産分割トラブルを防ぐためのポイントなどについてご説明いたします。
1.遺産に不動産があると遺産分割トラブルが起こりやすい理由
遺産に不動産があると遺産分割トラブルが起こりやすい理由として、主に次の3点が挙げられます。
・物理的に分けることが難しい
・金銭的価値が高い
・評価額が流動的である
現金や預貯金であれば1円単位まで公平に分割できますが、不動産は物理的に分割できないため、公平に分けることが難しいという問題があります。
その上、一般的に不動産は、他の財産と比べて金銭的価値が高いことから、誰が相続するかでもめやすいのです。特に、被相続人(亡くなった方)の配偶者や長男など、特定の相続人がその不動産に住んでいる場合には、相続人間で利害が対立しやすくなるでしょう。
また、不動産の評価額は流動的であり、その計算方法も法律で定められているわけではありません。そのため、評価額を巡って相続人間の意見が対立することも多いです。
2.不動産の遺産分割における基本的な方法
遺産となった不動産を分割するためには、以下の4つの方法があります。
・現物分割
・代償分割
・換価分割
・共有分割
どの方法を選択するかは、相続人間の話し合いにより自由に決めることが可能です。しかし、基本となるのは現物分割であり、現物分割が困難な場合に他の方法を検討していくことになります。
現物分割
現物分割とは、遺産をそのままの形で相続人が引き継ぐ分割方法のことです。
例えば、配偶者が自宅を、長男が賃貸マンションを、二男が別荘を引き継ぐことが考えられます。しかし、公平に遺産を分割するのは難しいことが多いです。
不動産が自宅の土地建物しかない場合でも、配偶者が自宅を、他の相続人は、現金や預貯金、株式などの有価証券、動産などを引き継ぐことも考えられます。しかし、不動産の他に高価な遺産がない場合には、この方法をとることはできません。
現物分割は、相続手続を簡便に進めやすいというメリットがある一方で、公平な遺産分割を実現するのが難しいことが多いというデメリットがあるといえます。
代償分割
代償分割とは、不動産を相続した人が、他の相続人に対して、法定相続割合に応じた代償金を支払うという分割方法のことです。
例えば、遺産として評価額3,000万円の自宅があり、相続人として長男と二男がいるとしましょう。長男が自宅を相続する場合には、二男に対して1,500万円(法定相続分である2分の1)の代償金を支払うことになります。
このように、代償分割によれば、公平な遺産分割を実現しやすくなるといえます。
しかし、代償金の額は、高額となることが多いため、不動産を相続した人に代償金を支払う経済的余裕がない場合、結局は、不動産を売却するなどして手放さざるを得ななくなる可能性があります。
また、代償金の額を計算する際には評価額が問題となるため、不動産の評価を巡って相続人間の意見が対立することも多いです。
換価分割
換価分割とは、不動産を売却し、得られた代金から諸経費を差し引いた金額を相続人間で分け合う分割方法のことです。
このようにして不動産を現金化すれば1円単位まで分割することが可能となるので、換価分割によれば、公平な遺産分割を容易に実現できます。
しかし、売却した不動産は第三者の手に渡ってしまうため、その不動産に住み続けたい相続人がいる場合など、手元に不動産を残したいニーズがあるケースでは、換価分割は適していません。
共有分割
共有分割とは、不動産を共有名義にして各相続人が引き継ぐという分割方法のことです。各相続人は法定相続割合に応じた共有持分を相続することになります。
こうすることで、公平な遺産分割を実現できますし、不動産を手元に残すこともできます。
しかし、不動産を共有名義にすると、他の共有者の同意がなければ売却や賃貸、リフォームなどができません。そのため、不動産の使用・収益に支障をきたすおそれがあります。
共有持分のみを売却することは自由ですので、一部の共有者が持分を売却すると、第三者との共有となってしまうことにも注意が必要です。
さらに、一部の共有者が亡くなると、さらなる相続によって共有者が増える可能性があります。共有者が増えれば増えるほど、名義変更の手続も複雑になりますし、不動産の使用・収益にも支障をきたしやすくなってしまいます。
そのため、共有分割は、問題の先送りにすぎず、あくまで最後の手段と考えておくべきであり、私は、これまでの経験上、おすすめしていません。
3.実際のトラブル事例とその解決策
当事務所が実際に取り扱ったトラブル事例として、亡き父親が残した不動産について、ご依頼者(長男)はまったく取得を希望していないにもかかわらず、家庭裁判所の審判で他の相続人(二男)との共有分割とされてしまったというものがありました。
この事例における問題点は、相続人である長男・二男のどちらも不動産の取得を希望していなかったことから、「どちらが不動産を引き取るか」ということです。
遺産分割では、まず現物分割を検討するのが基本です。本事案では、どちらが不動産を取得すべきかを判断する際に考慮すべき要素として、以下の事情がありました。
・本件不動産は二男の自宅から近く、ご依頼者の自宅からは遠くにある
・これまで二男が本件不動産を管理・利用してきた一方で、ご依頼者は本件不動産がどこにあるのかも知らなかった
・ご依頼者は被相続人から二男が本件不動産で畑仕事をするなどしていたことを聞いていた
当事務所の弁護士は、審判に対して抗告を申し立て、高裁で以上の事実を指摘した上で、本件不動産を二男が取得すべきであることを粘り強く主張・立証しました。その結果、高裁は、家裁の判断を変更し、概ね、当方の主張どおりの判断を出してもらうことができました。
なお、相続人の誰もが取得を希望しない不動産があるケースでは、一般的には換価分割が有効です。売却するのが難しい物件もありますが、あくまでも共有分割は最後の手段であり、安易に共有分割によるべきではありません。
4.不動産をめぐる遺産分割トラブルを防ぐためのポイント
不動産の4つの分割方法には一長一短がありますので、できる限り相続人同士で話し合いの上、全員が納得できる形で相続することが望ましいといえます。
そのためには、被相続人の生前から親族で話し合いを進めた方がよいでしょう。早期に話し合いを始めた方が、冷静に話し合いを進めやすいものです。
被相続人の死後、どうしても相続人間の話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所の遺産分割調停や審判で解決を図ることになります。
不動産を所有している方が生前にできる対策としては、遺言書の作成や生前贈与があります。
遺言書で不動産の取得者を指定しておけば遺産分割協議が不要となるので、トラブルの回避につながります。ただし、著しく不公平な内容の遺言書を作成するとトラブルが発生しやすいため、各相続人の遺留分に配慮することも重要です。
生前贈与では、高額の贈与税がかかる可能性もあるので、必要に応じて節税対策を検討することも重要となるでしょう。
5.遺産分割に関して弁護士に相談すべき理由
遺産分割協議でもめたときには、弁護士へのご相談をおすすめします。弁護士に遺産分割協議を依頼して、他の相続人との話し合いを代行してもらうことも可能です。法的な観点から冷静に交渉してもらうことで、早期に、かつ、柔軟な解決も期待できます。
遺産分割調停・審判が必要となった場合にも、全面的に弁護士のサポートを受けることができますので、有利な解決が期待できるでしょう。
被相続人の生前にご相談いただければ、有効で適切な内容の遺言書作成をサポートしてもらうことにより、遺産分割トラブルの予防を図ることも可能です。
6.当事務所のサポート内容
所沢の武蔵野合同法律事務所は、相続案件に特化した事務所です。
代表弁護士は、家庭裁判所の家事調停官としての経験も有しており、相続問題の解決実績は累計600件以上と豊富な経験を有しています。そのため、遺言書作成や生前贈与などの生前対策から遺産分割協議、調停・審判によるトラブル解決まで、安心してご相談いただけます。
また、所内に司法書士が在籍しており、代表弁護士が通知税理士として相続税申告も可能ですので、相続登記(不動産の名義変更)や相続税の申告、節税対策などの問題も含めて、ワンストップでの対応が可能です。
ご相談は初回60分まで無料です。不動産の遺産分割をはじめてとして、相続問題でお困りの方はお気軽に当事務所へご相談ください。