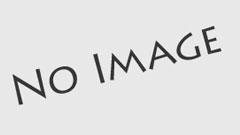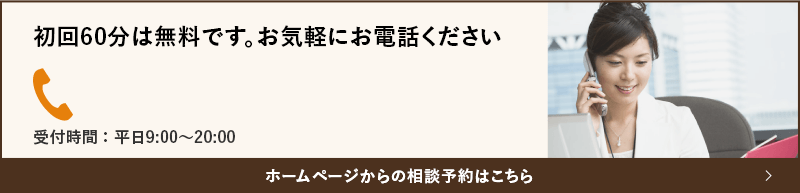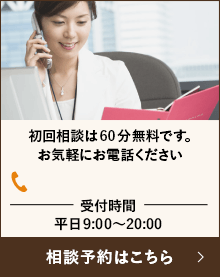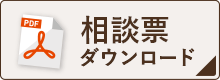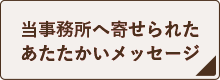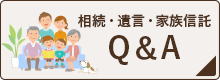強硬な主張・要求をしてくる相続人がいるときの対処法
遺産分割で強硬な主張・要求をしてくる相続人がいると、他の相続人の正当な相続分が脅かされてしまいます。
公平に遺産を分割しようとしても話し合いがスムーズに進まないでしょうし、最悪の場合は一部の相続人に遺産を使い込まれてしまうおそれもあるので、注意が必要です。
この記事では、強硬な主張・要求をしてくる相続人がいるときでも、公平な遺産分割を実現するための対処法をご紹介します。
Contents
強硬な主張・要求をしてくる相続人がいる理由
一部の相続人が強硬な主張・要求をしてくる理由は多種多様ですが、大きく分けると、次の2つのパターンに分類できます。
・相続のルールを知らない
・相続のルールは知っているが、多くの遺産を取得したいと考えている
相続で誰がどれくらいの遺産を取得できるかは、民法で定められています。しかし、すべての人が民法上のルールを正しく理解しているわけではありません。
実際には、「長男だから多くの遺産をもらえるはずだ」、「親と同居して親の面倒を見たのだから、他の兄弟よりも遺産を多くもらえるはずだ」などと、誤ったルールを信じ込んでいるために、強硬な主張・要求をしてくる相続人もいます。
なお、遺産の分割割合や分割方法は、相続人全員が合意すれば自由に定めることが可能です。このことを知っている相続人が、少しでも多くの遺産を自分が取得したいと考えて、強硬な主張・要求を他の相続人に押し付けてくるケースも少なくありません。
いずれにしても、ルールに反する主張・要求をされたとしても、他の相続人が泣き寝入りをする必要はありません。
強硬な主張・要求をしてくる相続人がいるときの基本的な対処法
強硬な主張・要求をしてくる相続人がいる場合でも、以下のように対処することにより、公平な遺産分割を実現することができます。
遺産分割協議
まずは、遺産分割協議において、強硬な主張・要求をしてくる相続人の説得を図ってみましょう。
正しい主張・要求をしている相続人同士で手を組み、強硬な主張・要求をしている相続人の説得を図ることにより、公平な遺産分割を実現できる可能性が高まります。
問題となっている相続人が相続のルールを知らずに誤った主張・要求をしている場合には、法律上のルールを正しく説明することで、説得できることがあるかもしれません。
遺産分割協議では、冷静に話し合いを進めることが大切です。感情的な対立がエスカレートして話し合いが進まない場合は、家庭裁判所での手続も視野に入れましょう。
遺産分割調停
遺産分割協議で話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所へ遺産分割調停を申し立てることになります。
調停は、家庭裁判所において、中立公平な立場の調停委員会を介して当事者が話し合うことで、合意による解決を目指す手続です。相続人同士が直接話し合うのではなく、調停委員会が間に入るため、冷静な話し合いが可能となります。
ルールに反する主張・要求をする相続人に対しては、調停委員会が法律上のルールを正しく説明し、場合によっては説得を図ってくれることもあります。
このようにして話し合いを進めることで、相続人だけで話し合う場合よりも、妥当な内容での合意が得られやすくなります。
相続人全員が合意すると調停が成立し、合意した内容を記載した調停調書が作成されます。調停調書には確定判決と同じ効力がありますので、その後に一部の相続人が意見や態度を翻したとしても、強制執行の手続を経ることで、調停調書の内容に従って強制的に遺産を分割することが可能です。
遺産分割審判
遺産分割調停でも合意に至らなかった場合は、調停不成立となり、自動的に遺産分割審判の手続に移行します。
審判では、当事者が提出した主張や証拠を裁判所が精査し、適正と認められる遺産の分割割合や分割方法が定められます。
当事者が審判書を受け取ってから2週間以内に即時抗告の申立てがなければ、審判が確定します。その後は、強制的に遺産を分割することが可能です。
即時抗告の申立てがあった場合には、高等裁判所で再審理されます。私の経験では、家裁の審判が納得できずに即時抗告の申立ての段階から受任した案件において、高裁で家裁の結論が覆った事例も複数ありますが、一般的には、新たに有力な証拠が提出されない限り、抗告審で結論が覆る可能性は低いです。
審判で適正な結果を得るためには、審判の手続に移行した段階で、主張をまとめて記載した書面や、未提出の証拠があればその証拠も提出することが非常に重要となります。
弁護士への依頼
以上の手続は、弁護士に依頼せず自分で進めることも可能です。しかし、相続人だけで話し合いがスムーズに進まない場合には、弁護士に遺産分割協議を依頼することも検討してみましょう。
弁護士は、依頼者である相続人の代理人として、他の相続人との話し合いを代理することができます。強硬な主張・要求をしてくる相続人に対しても、弁護士が対処してくれるのです。
弁護士が法律の専門家としての立場から、強硬な主張・要求をしてくる相続人と交渉することにより、その相続人も正しいルールを理解したり、無理な主張・要求を諦めたりすることは少なくありません。
このようにして、弁護士が遺産分割協議を代理することで、早期に、かつ、円満な解決が期待できます。
遺産分割調停や遺産分割審判が必要となった場合でも、複雑な手続は弁護士に任せることが重要です。
強硬な主張・要求をしてくる相続人がいるときには、当事者だけで争うよりも、弁護士のサポートを受けることで、公平な遺産分割を迅速に実現しやすいといえます。
場合によっては必要な法的手続
基本的な対処法は以上ですが、場合によっては、さらに専門的な法的手続を要することもあります。
例えば、強硬な主張・要求をしてくる相続人が遺産を使い込むおそれがある場合には、早めに審判前の保全処分の申立てを検討した方がよいでしょう。こうすることで、遺産分割調停の成立や審判の確定を待たずに、遺産の処分を禁じることが可能です。
既に遺産を使い込まれてしまった場合は、それを取り戻すために、不当利得返還請求訴訟や損害賠償請求訴訟を提起しなければならないこともあります。
また、遺言書がある場合で、遺言の有効性に疑義があるときには、公平な遺産分割を実現するために、遺言無効確認請求訴訟を提起することが必要となりますし、遺言の有効性に疑義がないときには、遺留分侵害額請求の調停や訴訟などが必要となります。
これらの法的手続は複雑ですので、最適な手続を選択して的確に進めるためにも、強硬な主張・要求をしてくる相続人がいるときは、早めに弁護士に相談してみた方がよいでしょう。
まとめ
最後になりますが、ときには、強硬な主張・要求をしてくる相続人の意見が正しい可能性もあることを知っておきましょう。
例えば、長年にわたって被相続人(亡くなった方)の事業を手伝ったり、被相続人の療養・看護に努めてきたりした相続人が、多くの遺産の取得を主張・要求するようなケースです。このような場合、その相続人は寄与分を主張することにより、法定相続分よりも多くの遺産を取得できる可能性があるのです。
遺産分割で感情的に対立すると、各相続人が自分の利益ばかりを考えてしまい、ルールに反した主張をすることにもなりかねません。
弁護士にご相談いただければ、法律上のルールに則り、適正な解決に導いてもらえます。
もちろん、相手の主張・要求がルールに反している場合には、弁護士から説得を図ってもらえますし、話し合いによる解決が難しい場合には、迅速に法的手続を進めてもらえます。
強硬な主張・要求をしてくる相続人がいることでお困りの際は、お気軽に弁護士へご相談ください。
この記事の執筆者
- 弁護士 元さいたま家庭裁判所家事調停官
-
専門分野:相続、不動産、企業法務
経歴:埼玉県立熊谷高校から早稲田大学法学部に進学。卒業後、平成16年に弁護士登録。平成21年に地元である埼玉に弁護士会の登録替え。平成26年10月より、最高裁判所よりさいたま家庭裁判所の家事調停官(いわゆる非常勤裁判官)に任命され、4年間にわたり、週に1日、さいたま家庭裁判所に家事調停官として勤務し、数多くの相続事件を担当。平成30年5月に武蔵野経営法律事務所を開業し、現在に至る。
家事調停官の経験を活かし、相続事件の依頼者にとって最適な解決に導くサポートを実施している。
家事調停官時代の件数を含めて、相続事件の解決実績は500件以上に上り、地域内でも有数の実績である。