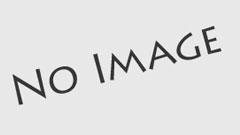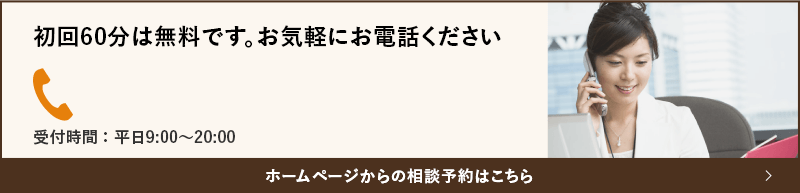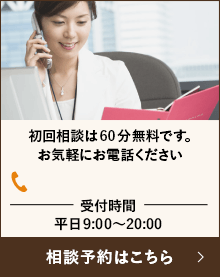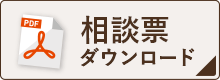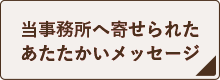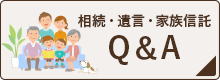遺産相続で相手方に弁護士が付いたときのリスクと注意点
遺産分割で他の相続人と話し合いをしている途中で、相手方が弁護士に依頼することは少なくありません。
相手方に弁護士が付いたからといって慌てる必要はありませんが、こちらも適切な対応をとらなければ、遺産分割協議で不利になってしまう可能性が高いので、注意が必要です。
この記事では、遺産分割で相手方に弁護士が付いたときのリスクと注意点、さらには、自分も弁護士を付けるべきかについても解説します。
Contents
遺産相続で相手方に弁護士が付いたときに生じるリスク
相手方に弁護士が付いたとき、自力で遺産分割協議を進めようとすると、以下のリスクが生じますのでご注意ください。
対等に交渉することは難しい
弁護士は法律のプロであり、交渉術にも長けています。そんな弁護士が相手方に付いた場合には、こちらにも相応の専門知識や経験が求められます。
しかし、ほとんどの方は相続に関する法律に精通しているわけではないでしょうし、交渉ごとの経験が豊富なわけでもないでしょう。
一般の方が弁護士を相手に対等な交渉をするのは困難なので、そのままでは相手方の有利に遺産分割協議が進められてしまいます。
不利な遺産分割案を押し付けられやすい
相手方に付いた弁護士といえども、状況にもよりますが、けんか腰で対応してくるわけではありません。通常は節度を保った態度で、言葉遣いも丁寧であり、いっけんすると親しみやすい印象を与える弁護士も少なくありません。
しかし、話の内容は相手方にとって有利になるように練られており、言葉巧みに説得してくることがほとんどです。
相手弁護士の話を聞いているうちに、「こうするしかない」、「Win-Winの解決策だ」という気持ちにさせられ、不利な内容であることに気づかないまま、遺産分割協議書にサインをしてしまうことにもなりかねません。
遺産分割調停・審判を起こされることがある
遺産分割協議がなかなかまとまらない場合、相手弁護士は家庭裁判所へ遺産分割調停や審判を申し立てることがあります。
普通の人なら、裁判所での手続きは大ごとに感じてしまうでしょう。他の相続人と意見が食い違っていたとしても、なるべく話し合いで解決したいと考えるはずです。裁判所から書類が届くと、悪いことをしたわけではなくても驚いてしまう人がほとんどではないでしょうか。
しかし、弁護士にとって裁判手続きは日常業務の一環であり、特別なことではありません。
多くの場合、調停や審判を起こされる前に、相手弁護士から最終の提案があります。そして、「この案に応じていただけない場合は、法的措置をとります」などと告げられます。そのとき、法的措置を恐れて不当な遺産分割案に応じてしまわないように、注意することも大切です。
遺産相続で相手方に弁護士が付いたときの注意点
相手方に弁護士が付いたときには、以下の3点にご注意ください。
相手弁護士からの連絡を無視しない
相手方が弁護士に依頼すると、まず、その弁護士から内容証明郵便が届きます。その内容は、「話し合いの機会を持ちたいので、2週間以内(あるいは、10日以内など)に当事務所までご連絡ください」というものです。
もし、所定の期限内に連絡しなければ、ほとんどの場合は相手弁護士の方から電話や普通郵便などで連絡があります。その連絡を無視し続けると、最終的には遺産分割調停や審判を申し立てられることになります。
相手弁護士からの連絡を無視したからといってペナルティーはありませんが、話し合いを始めなければ何も解決しませんので、早めに連絡しましょう。
相手方本人へ直接連絡しない
相手弁護士から届く内容証明郵便には、「本件に関するご連絡はすべて当職へ」ということも記載されています。したがって、その後は相手方本人に対する直接の連絡は控えましょう。
直接連絡をしたとしても、「弁護士を通してください」と返答されてしまいます。執拗に連絡をとろうとすると相手方の感情を逆なでしてしまい、遺産分割での対立がエスカレートすることにもなりかねません。
相手方が弁護士に依頼した以上は、その弁護士が相手方の代理人となりますので、交渉相手はその弁護士となります。
相手弁護士からの質問に対する回答はいったん保留する
相手弁護士との交渉では、どうしても相手方のペースで会話が進むことになりがちです。
交渉のテーブル上では、相手弁護士からの質問に対して、断定的な回答をすることは控えましょう。なぜなら、相手弁護士は交渉が相手方にとって有利に進むように話を組み立てて、言葉巧みに会話を誘導することがほとんどだからです。
相手弁護士から重要な判断を求められた場合には、その場で回答せずにいったん持ち帰り、家族と協議したり、別の弁護士に相談したりしてから、適切な回答をするように心がけましょう。
遺産分割協議書などの書類へのサインを求められた場合も、その場でサインせず、いったん持ち帰ることです。
相手方が弁護士を付けたら自分も弁護士を付けるべき?
遺産分割で必ず弁護士を付けるべきとまではいえませんが、相手方に弁護士が付いた場合には、こちらも弁護士を付けた方がよいといえます。
誰しも、遺産分割は円満に進めたいと考えるはずです。それにもかかわらず、費用を支払ってまで弁護士に依頼するということは、譲れない主張が相手方にあるということです。
相手方の主張がこちらにとって納得できないものであったとしても、弁護士が付いた後の交渉では感情論を抜きにして、法律や裁判例に基づく理論・理屈で説得しなければなりません。このような交渉において、一般の方は弁護士に太刀打ちできないのが実情です。
したがって、相手方に弁護士が付いた場合には、自力で無理をせず、こちらも弁護士のサポートを受けることをおすすめします。
遺産相続で弁護士に依頼するメリット
遺産相続で弁護士に依頼することには、以下のメリットがあります。
知識不足による損失を回避できる
相続に関する法律の規定は、非常に複雑です。専門家でなければ、そのすべてを正確に把握するのは困難です。そのために、遺産分割では、自分に有利な規定があることを知らないことが原因で損をするケースが多々あります。
しかし、弁護士のサポートを受けることで、知識不足をカバーすることが可能です。こちらに有利な制度や権利があれば弁護士が教えてくれますし、相手方の主張に対する反論も弁護士が考えてくれます。
弁護士が有する知識と経験を活用することで、最善の解決が期待できるのです。
相手方との交渉や調停・審判を任せられる
弁護士は、依頼者の代理人として活動してくれます。問題解決のために必要な手続きは全面的に、弁護士に任せることが可能です。
遺産分割協議は弁護士同士での交渉となりますので、自分で直接、相手方や相手弁護士とやりとりをする必要もなくなります。
交渉がまとまらず、遺産分割調停や審判になった場合にも、弁護士が代理人として全面的にサポートしてくれます。
調停期日には当事者が裁判所へ出頭する必要がありますが、弁護士も同席し、調停委員とのやりとりをサポートしてくれるのです。裁判所へ提出すべき書面はすべて、弁護士が作成し、提出してくれます。
相続手続きのサポートも受けられる
遺産分割協議や調停、審判によって遺産の分割方法が決まった後にも、相続に関するさまざまな手続きを行う必要があります。
預金口座や生命保険などの解約・名義変更などは自分でもできますが、不動産の名義変更(相続登記)や相続税の申告などは、専門家に依頼する必要性が高いことが多いです。
しかし、遺産相続に強い弁護士は司法書士や税理士など、他士業の専門家と連携して対応してくれることが多いので、その場合には各種手続きのサポートも受けられます。相続問題を全般的にワンストップで解決できることも、大きなメリットのひとつといえるでしょう。
遺産相続で依頼する弁護士の選び方
相手方に弁護士が付き、こちらも弁護士への依頼をお考えの場合には、遺産相続に強い弁護士を選ぶことが大切です。ここでは、その選び方のポイントをご紹介します。
相続問題の解決実績が豊富にあるか
弁護士を選ぶ際に最も注目すべきポイントは、その弁護士に相続問題の解決実績が豊富にあるかどうかという点です。
弁護士にも得意分野・不得意分野があり、相続問題をあまり取り扱っていない弁護士も数多くいます。相続問題について適切なアドバイスやサポートを提供するためには、弁護士側に経験が求められるのです。
相手方に弁護士が付いた場合は特に、相続問題の解決実績が豊富な弁護士のサポートを受けなければ、相手弁護士と対等に渡りあえないおそれもあります。
話しやすく、説明が分かりやすいか
弁護士に依頼する前には、まず法律相談を利用することになりますが、その際には弁護士の人柄にも注目しましょう。
話を聞いてくれない弁護士や、説明が分かりにくい弁護士に依頼すると、親身に対応してもらえないおそれもあります。何よりも、ご依頼者にストレスがたまってしまうでしょう。
無料相談を利用して複数の弁護士に相談しても構いませんので、弁護士の人柄もチェックし、ご自身と相性が合うと感じる弁護士に依頼するのがおすすめです。
料金設定が適切か
相続問題の解決を弁護士に依頼するためには、相応の費用がかかります。
具体的な金額は弁護士によって異なりますが、実績が豊富で信頼できる弁護士のほとんどは、相場の範囲内で料金を設定しているものです。費用が高すぎる弁護士や、逆に低すぎる弁護士に依頼するのは考えものです。
法律相談の際には、依頼に必要な費用の見積もりを必ずとりましょう。インターネットでは、さまざまな事務所の料金体系を参照できますので、比較した上で、料金設定が適切な事務所に依頼することをおすすめします。
他士業の専門家と連携しているか
相続問題では、司法書士や税理士など、他士業の専門家によるサポートを要することも少なくありません。
そのため、弁護士に依頼する前に、他士業の専門家と連携してワンストップで対応してくれるかも確認しておくことが望ましいです。ワンストップでの解決を図ることにより、時間・費用・労力のすべてを削減することが可能となります。
まとめ
遺産分割で相手方に弁護士が付くと、その弁護士が交渉相手となります。対等に交渉するために、まずはこちらも遺産相続に強い弁護士に相談してみた方がよいでしょう。
所沢の武蔵野合同法律事務所では、遺言や相続問題に力を入れております。これまで解決に導いてきた相続事件は500件を超えており、相続問題に関する豊富な実績がございます。
司法書士や税理士をはじめとする他士業の専門家とも連携し、ワンストップでの対応が可能ですので、相続問題ならどのようなことでもご相談いただけます。
初回相談は60分まで無料ですので、相手方に弁護士が付いてお困りの際は、お気軽に当事務所へお問い合わせください。
この記事の執筆者
- 弁護士 元さいたま家庭裁判所家事調停官
-
専門分野:相続、不動産、企業法務
経歴:埼玉県立熊谷高校から早稲田大学法学部に進学。卒業後、平成16年に弁護士登録。平成21年に地元である埼玉に弁護士会の登録替え。平成26年10月より、最高裁判所よりさいたま家庭裁判所の家事調停官(いわゆる非常勤裁判官)に任命され、4年間にわたり、週に1日、さいたま家庭裁判所に家事調停官として勤務し、数多くの相続事件を担当。平成30年5月に武蔵野経営法律事務所を開業し、現在に至る。
家事調停官の経験を活かし、相続事件の依頼者にとって最適な解決に導くサポートを実施している。
家事調停官時代の件数を含めて、相続事件の解決実績は500件以上に上り、地域内でも有数の実績である。
最新の投稿
 コラム2025.07.25強硬な主張・要求をしてくる相続人がいるときの対処法
コラム2025.07.25強硬な主張・要求をしてくる相続人がいるときの対処法 コラム2025.04.16遺産相続で相手方に弁護士が付いたときのリスクと注意点
コラム2025.04.16遺産相続で相手方に弁護士が付いたときのリスクと注意点 コラム2025.03.12連絡を無視・拒否する非協力的な相続人がいるときの相続手続き
コラム2025.03.12連絡を無視・拒否する非協力的な相続人がいるときの相続手続き コラム2025.02.28遺産を独り占めしようとする相続人がいるときの対処法
コラム2025.02.28遺産を独り占めしようとする相続人がいるときの対処法